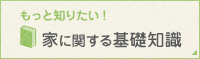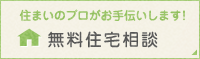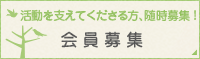杉の勉強会
日本で最も蓄積量の多い樹種である杉。
今回、勉強会を開くに至った経緯として、最近の技術的な革新や研究などから、新しい情報や解釈など、これまでの認識から進化していることがあれば学びたい、という思いがありました。
普段から杉の多様さ、奥深さは様々な場面で感じることがあります。その理由の根本に、500年以上の林業の歴史の中で多くの品種が生まれ (突然変異もあり)、産地による違いも掛け合わされたことがあげられるようです。
多様さには、多様な対応が求められるということでしょうか。乾燥方法ひとつをとっても実に多くの工夫があり、求める品質により利点欠点もでてきます。天然乾燥であれば、材内部の精油の減少はどの温度帯よりも少なく、成分(ヘミセルロース等)の熱分解もなく、見た目にも本来の色艶を保てるとのことです。
しかし、建築業界では、計画から着工に十分な時間が確保できないことが多く、コストバランスが求められます。
その対応として新しい技術や工夫が生まれてきているため、状況に応じて適した方法を選んでいきたいと感じます。
例えば、内装材は、人が長時間過ごす空間としての快適性から低VOC、高調湿機能、適度な放散精油などを重視し、構造材は、強度・耐久性・材の内部割れが発生しない方法についてなどです。杉の精油には良い効果が期待されていますが、精油の含有量が多い品種は強度が低くなりがちとのことでした。様々な側面から知ることが大事です。長く木を生かす方法として、伐採方法や時期(新月伐採等)についても、実証や経験則、講演者の見解など、一筋縄にはいかない解釈や工程における工夫例が示されました。
私たちの要望を軸にテーマの解釈を広げていただき経済主体から人間主体であることを取り戻す大切さ、人の快適性の重要性が語られました。伐採された木がその寿命を全うでき、人を元気づけ長く暮らしを共にできるように、品質を活かし、適材適所にもちいることの大切さを改めて学びました。 [ 梶 純子 ]
4月24日(水) 大阪木材会館 にて開催 講師:(一社)大阪府木材連合会アドバイザー吉良靖男 氏